緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年7月8日
浜松ものづくりマイスターのご紹介
令和5年度認定者
渡邊隆氏(株式会社エコム)

【専門分野】加熱設備における燃焼調整技術
工業炉(加熱設備)は、鉄や銅・アルミニウムに熱を加えて自動車や航空機・電化製品の部品に加工するための設備や、陶磁器やガラス・セメントなどのセラミックスを製造するための設備など日本国内に約4万基あると推測されています。それら工業炉からのCO2排出量は日本全体の約15%といわれており、工業炉の熱計測データの解析・分析技術を用いた熱最適化による省エネ技術は、CO2排出量の削減に向けた重要な技術の一つとなります。
【渡邊さんの業務内容】
渡邊さんは燃焼炉に関する技術営業、メンテナンス、人材育成の業務全般に取り組んでいます。緊急のメンテナンス依頼に対しても長年の経験値を生かし、不具合箇所の可能性から優先順位を割り出して対処法を提案し、半数近くを電話で解決しています。顧客からの相談を待つ「受け身」ではなく、もしものトラブル対応ができるよう、顧客に向けたメンテナンス講習を実施しています。
【相談対応内容】
加熱設備の計測データの解析技術・熱分析技術について、外部向けの講習実施や若手育成など。
牧田真政氏(株式会社牧田技研)

【専門分野】スピンドルのオーバーホール、マシニングセンタテーパー部の研磨技術
工作機械の心臓部とも言われているスピンドルは消耗が激しく、修理や買い替えとなると長期間生産を止めることとなり、金額も莫大な費用が必要でした。主要メーカーを下支えする中小企業にとっては積年の問題でありながらも自社では解決が難しく製造メーカーに委ねる他はありませんでした。この課題に対応可能なスピンドルオーバーホールによる修繕とマシニングセンタテーパー研磨による精度復活は、浜松でも唯一無二の技術として高く評価されています。
【牧田さんの専門技術】
工作機械の重点工具であるスピンドルを図面や仕様書なしでもオーバーホールすることで新品同様に再生する技術。現行では図面や仕様書を保有する製造メーカーでの修理対応を求める以外に方法がなく、顧客の生産活動を半年以上の長期間停止させるリスクが生じていました。牧田氏の技術を利用したオーバーホールを実践した場合、納期は約1ヵ月で新品同様に再生でき、生産活動の停止期間を最小限に抑えることが可能になりました。また、自社で開発した新機器を用いたマシニングセンタテーパー研磨では、主軸の不具合を分解不要で出張・短時間にて精度復活を実現できます。どちらもスピンドルに対する知識と経験がなければできない高度な専門技術です。
【相談対応内容】
スピンドルのオーバーホール技術、マシニングセンタテーパー研磨について、地域企業や学生などを対象に、技術相談や工場見学の受け入れが可能です。
令和4年度認定者
山本伸太郎氏(株式会社日本設計工業)

【専門分野】協働ロボットプログラミング
人間の作業員の代わりに働く「産業用ロボット」に対して、人間と一緒に働く「協働ロボット」は、人の作業を手助けし、安全で効率よく、しかも長時間にわたる稼働が求められます。山本さんは、作業現場でのヒアリングを丁寧に行うことで工程間の連動を独自の視点で観察・分析し、動作命令をプログラミングします。人間が無意識に行っている工夫や改善を他の技術者より多く気づきロボットの動作に落とし込み、「熟練作業者」のような動作ができる協働ロボットの設計を実現しています。
【会社の事業】マテリアルハンドリングを提供
株式会社日本設計工業は、生産現場の搬送ラインや自動化装置など、ロボットを組み込んだマテリアルハンドリング(マテハン)システムを提供しています。とりわけ協働ロボットシステム開発の分野では、PLC制御技術に画像検査のノウハウを組み合わせて多様な業界の自動搬送化や省力化に貢献しています。近年、こうした仕事領域は、「ラインビルダー」や「ロボットシステムインテグレータ」と呼ばれています。
【相談対応内容】
「協働ロボットプログラミング」に関して、「協働ロボット概論」をはじめ、ものづくりの技術相談や技術・技能をテーマとした講義、ものづくり精神や人生経験などの講演に対応しています。また、株式会社日本設計工業の本社において、実際に稼働する協働ロボットや設計・組立の現場見学にも対応しています。
山本伸太郎氏紹介チラシ(PDF:2,032KB)
令和3年度認定者
松井敦仁氏(藤本工業株式会社)

【専門分野】バリ取りロボットのティーチング技術
バリ取りとは、金属鋳造やプラスチック・ゴムなどの加工・成形の際に発生する突起や残留物を「バリ」と呼び、これらを手作業や自動化ロボットによって取り除く作業のこと。バリ取りが適切に行われないと品質面のトラブルが発生するため、極めて重要な工程となる。
10年を超えるバリ取り作業経験の中で、複雑なバリ取り事例を数多く体験。また、製造技術や生産管理分野などの実務経験を重ねたことで、「バリ取りの自動化」に着手。ロボットへのティーチング技術を確立したことで、品質とサイクルタイムを両立させたプログラムの構築を実現しました。これにより、製品の短納期化・工程省略が果たされ、生産性や品質が向上しました。同時に、これまで職人による専門作業に委ねられ、製造プロセスの中で時間的・労力的に埋もれていたバリ取り工程のポジションが確保され、その重要性と責任管理がより明確になるなど、イノベーション的な価値をもたらしました。
手作業によるバリ取りを極めていくこくは、職人としてひとつの道です。しかし、量産で作業していく中では、時間と効率もまた、企業にとっては欠かせない視点です。職人の技術とロボットの融合は、まだまだはじまったばかりで試行錯誤の連続です。その中から、バリ取りのスタンダードを築くことは、イノベーションという意味でも大きな価値があります。求められていることに、正しい判断力で応えていくことが、私の役割であると感じています。
令和2年度認定者
中前勉氏(浜松ガスケット株式会社)

【専門分野】ガスケット設計・製造
エンジンなどのさまざまな接合部のシールに必要とされるガスケットには、圧縮復元特性、耐熱性(耐寒性)、耐薬品性、長期安定性、メンテナンス性が求められます。ガスケットは使用する部位で、シール対象物(燃料、オイル、水、ガスなど)や条件(エンジン特性による)が異なるため、目的に合わせた材質を選定し、構造を設計します。開発には機能を保証する評価を行っています。
私はもともと車好きで、エンジンに関わる仕事への強い憧れがありました。入社と同時に、当時最先端のメタルガスケット製造技術、エンジン構造などを他社で研修し、その後自分で設計し製作した試作品を評価することでガスケットに関する知識と技術を習得しました。エンジンやいろいろな工業製品に必要不可欠なガスケットの試作開発から量産対応まで、全てを一貫して経験したことが今のスピーディーな試作開発につながっています。
難解なオーダーにも応えるため、メーカーとのコミュニケーションから課題の本質を見抜き、これまでの製造データベース、インスピレーション、経験をもとにガスケット製品の設計をしています。まずは要求機能を設定してスピーディーに試作と評価を繰り返します。試作品の了承が得られると、量産対応の準備に入ります。効率的な工程設計、量産に必要な金型(金属などの硬い材料を打ち抜く型)、成形型(金属線とガスケット材を押し固める型)やトムソン型(合板に刃を埋め込んだ型で柔らかい材料を打ち抜く型)、治具などの手配や製作、安定した品質で量産できる工程の作り込みをします。
大石誠一氏(丸大株式会社)

【専門分野】竹材加工に適した丸鋸超硬刃物の開発・製造
木材の切断等に用いる超硬刃物は切り口が美しいだけでなく、高速切断が可能で耐摩耗性にも優れています。刃先の超硬を丸鋸に固定するにはロー付け(接合部材より融点の低い合金を溶かして接着剤として用いる接合法)を行います。木材の中でも特に竹材は、外皮が固く、繊維が針状で表面にささくれができやすいため加工が難しく、特殊な超硬刃物による加工が必要です。
私は幼い頃からものづくりが好きで、既に小学4年で旋盤や溶接機を使っていた記憶があります。就労後は50年以上にわたり技術や知識の習得に努めながら、「誰も作ったことがないものを作りたい」という一心で超硬刃物の開発製造に取り組んできました。その経験と技術を、精密青竹切断機や常温生竹微粉末製造機といった新発想の製品開発へと進化させることができました。
丸鋸の表面に溝を設けることでロー付けの際に生じる熱を放熱し、温度差による刃物の歪みを抑える技術を開発。その結果、より硬い超硬を刃先に用いることができ、耐久性にも優れた超硬刃物を実現。この画期的な技術は英国のオックスフォード大学でも紹介され、世界の注目を浴びました。その後は名古屋大学との共同研究により竹の切削技術の開発に着手し、210mmの小径の鋸を使って容易かつ滑らかに竹を切断する「精密青竹切断機(竹ちゃん)」の開発に成功。続いて、生竹の食用品超微粉末を製造する「常温生竹微粉末製造機(PANDA)」を開発しました。竹を5μmに切削するのは世界唯一の技術です。
令和元年度認定者
鈴木育夫氏(株式会社大場鋳造所)
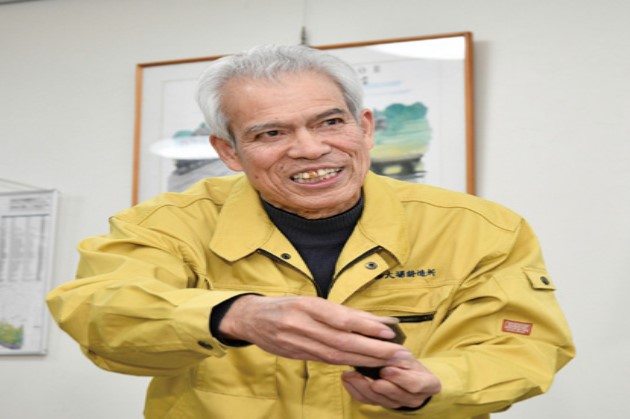
【専門分野】銑鉄鋳物
溶かした金属材料を型に流し込む鋳造加工は、複雑な形状の部品を簡単に作り出せるため、自動車や機械の部品を始め日用品などにも使われています。高温で流動性のある溶湯(ようとう/溶かした鉄などの素材)を鋳型(いがた/作りたい形と同じ形の空洞部を持つ型)に行き渡らせ、鋳型内部で凝固・収縮させ、製品を完成させます。
「溶けた金属を、どこからどのような経路で流しこめば、ムラや欠陥のない鋳物を仕上げることができるのか?」を50年以上にわたって経験してきました。製品は、例えばショベルカーなどの建設機械の内部に組み込まれるので、日常で目にすることはありませんが、保安に関わる重要な部品です。銑鉄鋳物技術でしか作ることのできない特別な部品であることが大きな誇りです。
長年の経験から砂型鋳造(完成品と同じ形の木型や樹脂型を用いて、空洞を成型した砂型に溶湯を注ぎ、鋳物を成形する)に精通し、求められる製品の鋳造方案の仕事をしています。製品依頼者の元を訪問し、要求仕様に基づいて製品の形状や質量、コスト、納期を明確にし、用いる材料や鋳造法を決定します。
平成30年度認定者
杉山和男氏(有限会社杉山木型製作所)

【専門分野】木型設計製作
戦後の高度経済成長に伴い、木型業界も発展してまいりました。特に浜松市は自動車・オートバイ産業が盛んで、この産業には木型の存在が不可欠でした。木型師として最高の花形が、自動車やオートバイのエンジンとその関連部品を作るための鋳造用木型をハンドメイドで作れることでした。
私は46年の本業務の中で自動車用部品の主要な鋳造用木型の製作経験を積んできました。木型業界に入る前に、設計事務所で自動車用部品等の設計業務に携わっていた経験を生かし、図面から設計者の意図を汲んで、木型製作の後工程(鋳造工程、機械加工工程)までを考えた形状提案ができることを強みとしています。
木型業界のデジタル化や自動車業界の成熟化で、手加工での木型製作の需要は減りつつあります。しかし、産業用ロボットを作るため各種部品の鋳造用木型の需要は増えており、形状の複雑さ、短納期を求められることから、職人の手加工も大いに期待されていると感じています。
現在、自社の後継者に技能伝承しながら、地域の有志勉強会「浜松木型研究会」(浜松の木型業者10社で結成)においても後進の指導や次世代技能・技術者への啓発を行っています。
平成29年度認定者
三輪政春氏(ミワ技研)

【専門分野】機械加工(治具部品の加工)
私は入社してまず生産設備のオーバーホール担当として、機械の修理、補修部品加工に携わりました。その後、加工担当となり、治具製作することで旋盤技術を修得。社内のあらゆる機械の治具づくりに対応できるよう、フライス盤、ボール盤、研磨などの操作を覚えたことで、一つ一つの治具が果たす役割や重要性を理解しました。
治具は生産設備の一部品ですが、その実用性や耐久性の高さが、製品の品質や低コスト化、生産性の向上に大きく貢献するものです。図面通りに作るだけでなく、試作品をもとに、これまでの経験、勘から治具の材質や加工の仕方を試行錯誤します。独自の創意工夫で、従来の工法を革新できることが大きなやりがいです。
「安全な作業は作業の入り口」「基本なくして応用なし」の2つを常に肝に銘じています。安全第一かつ基本に忠実に、そしてあらゆる挑戦を惜しまない姿勢を大切にしています。今後は自分の身に付けた技能を若手に伝承していきたいです。社内だけでなく、浜松のものづくりが一層元気になってほしいと思います。
山本真史氏(株式会社桜井製作所)

【専門分野】きさげ加工
きさげ加工の仕事に携わるようになり9年が経ちます。師匠に教えてもらいながら、初めは荒削りを担当し、徐々に中引き、仕上げと任せてもらえるようになりました。機械によって、きさげ加工が必要な面の多さや複雑さは異なりますが、約1カ月かけてようやく1台分のきさげ加工が終わるという大きな案件に携わることもあります。
弊社では自社の工作機械はもちろん、他社で作られた工作機械の修理やオーバーホールの仕事もあります。その際には、何十年も前にきさげ加工された面を見ることもあり、その当時の職人技を参考に自分の技術を磨く毎日です。
また逆に、今出荷している工作機械がオーバーホールされる時、私が施したきさげ加工が若手のきさげ職人の目に触れることになります。その時に「こんなきさげ加工を目指したい。」と思ってもらえるような、職人技の仕上げを残せたらと思います。
実はきさげ加工のような技術は世界中にあり、その方法もさまざまだと言われています。今後は自分の語学力を生かして、世界を舞台にきさげ加工技術を学ぶ機会を作り、お互いにより高い技術レベルを目指した交流を図っていきたいと思います。
平成28年認定者
橋本秀比呂氏(橋本螺子株式会社代表取締役会長)

【専門分野】工業用規格ねじ・医療用ねじ(骨固定インプラント)など、各種ねじ類の製造・販売
先代の父が「ねじ」の商売を始めたのが昭和30年。私の生まれたのが昭和29年。ですから「ねじ」と共に育ったと言っても過言ではありません。私の周りにはいつも「ねじ」があり、「ねじ」が私の「遊び道具」でもありました。その思い出が「ねじブロック」開発の基となりました。私たちの身の回りには、たくさんの「ねじ」があり、家電製品・車・パソコン・携帯電話などすべてに「ねじ」が使われています。「ねじ」はものづくりの原点と言ってもいいでしょう。このように私たちの生活は「ねじ」に支えられているにもかかわらず、意外と注目されることが少ないのが現実です。その「ねじ」の役割や重要性を一般の方にも理解してほしい、大切さを知ってほしい。そんな思いで生まれたのが「ねじブロック」です。「ねじブロック」が子供たちの創造力をかき立て、ものづくりの世界に興味をもつきっかけになればと念じつつ、各地で「ねじブロック」の展示会やワークショップを開催するなど「ねじ」を通じて、ものづくりの啓発普及活動を展開しています。「ねじブロック」が将来の「ものづくりはままつ」に少しでも貢献できればと考えております。
現在、弊社の売上の60%が規格ねじとオーダーパーツ、20%が医療分野、残り20%がその他(防災・救命また「ねじブロック」など)の事業です。今後は、医療分野を50%にまで拡大していきたいと思います。そのために医療現場のニーズを正しく掴み、求められる材質や強度を最適にした形として、お応えしていくことが大切だと考えます。また企業間連携では、自社だけでは成し得ないことも、他社の技術と知恵を掛け合わせることで、低リスクでスピーディーに、よりクオリティの高いものを作り出していけることも実感しています。
渥美好康氏(株式会社明和工業)

【専門分野】SUSプロペラのバランス測定・調整(バフ研磨)
私が担当するSUSプロペラのバランス測定・調整は、初めにプロペラのバランスを測定するところから、バフ研磨による調整、最終検査までを一人で行っています。「自分だけが携わる」からこそ責任は重大で、初めの頃は慎重に何度も研磨しては測定し、また研磨しては測定し、を繰り返していましたが、今は、ほぼ一発で決めています。バランスの調整には、いかに最初の測定で「どの翼のどの部分をどれだけ削ればいいのか」を瞬時に、しかも正確にはじき出せるかが非常に重要になります。「お客さまに絶対に迷惑をかけられない」というプレッシャーを、毎日自分にかけ続けてきたことで、ようやく取引先からも高い評価をいただけるようになったと思います。
当社では、生産システムの効率化を極限まで追求するため、特にオペレーターの自主保全体制づくりや人材育成のための教育・訓練の体制づくりに力を入れています。バフ研磨工程においても、技術を体で覚えるための教育ブースを工場内に設置しています。作業の姿勢、バフに押し当てる圧力や角度を毎日繰り返し確認することで、バフ研磨の技術が自然と身に着いていきます。またブースには、故障部品を並べて、何が原因でどんな不具合が生じたのか、失敗を共有できるようにしています。今後の目標は、自分と同じレベルの技術をもつ人材を育てることです。チームで作業する仕事では、前工程を担当する者の技術がレベルアップしない限り、仕上げの完成度に差が出てきます。新入社員や海外からの実習生など、性格の違いや言葉の壁、作業の癖など、さまざまなハードルがありますが、身をもって丁寧に覚えさせること、失敗を恐れないチャレンジ精神を育てることを大切に、日々、教育や訓練を行っています。
平成27年認定者
沢根孝佳氏(沢根スプリング株式会社取締役会長)

【専門分野】ばねづくり(塑性加工)
ばねは、線材や板材をコイル状に巻いたり曲げたりし、熱処理や表面処理などの工程を経て製作します。ばねの形状により、圧縮ばねや引張ばね、ねじりばね、また板ばねなど、様々なばねの種類があります。ばねには、力によって変形し、伸びたり縮んだりし、その力が除かれると元の形に戻る復元力、力によって変形したときにエネルギーを蓄積し放出するなどの特徴があり、他の機械要素とは全く異なったユニークな部品であるといえます。沢根スプリングでは、自動車関連などの量産リピート品のばねの他、1本のばねからの小口スポット品の注文を全国から受注し、生産してい
ます。
雪山有司氏(有限会社雪山シボリ取締役会長)

【専門分野】ヘラ絞り(塑性加工)
ヘラ絞りは、金型の先端に加工する円板を取り付けて回転させ、「ヘラ棒」と呼ばれる工具を円板に押し付けて金型の形状に添わせて変形させていく加工技術です。ヘラ棒を当てる角度や力の入れ具合に微妙な力加減が必要であり、力加減を誤ると折れて曲がってしまったり、破れが発生しやすいことから、「経験と勘」がものをいう技術であるといえます。雪山シボリでは、主にプレス加工で製造することができないバイクのマフラーや集塵機のダクトの成型、また最近では管楽器のミュート(消音器)など特殊な形状を要求される製品や試作品の加工を行っています。加工する材料は主に鉄、アルミニウム、ステンレス、真鍮、銅、チタンなどです。
平成26年認定者
岩上勝氏(株式会社三創楽器製作所代表取締役)

【専門分野】古典楽器の製造
楽器の街・浜松で40年近くにわたって、チェンバロやクラヴィコード、小型パイプオルガンなどの古典楽器を製作しています。特にチェンバロは、海外の交響楽団で使用される本格的なものから、家庭で楽しめる普及モデルまで幅広く手掛けています。チェンバロは15世紀から18世紀末頃のヨーロッパを中心としたバロック音楽の演奏に使われていた古典楽器です。撥弦楽器といって、鍵盤を用いて弦を弾くことで倍音の豊かな音色が響きます。イギリス、フランス、イタリア、ドイツなど、作られていた国や地方によって様式が分かれており、音色にもそれぞれ特徴ありました。その後、ピアノの完成度が高くなるにつれて衰退しましたが、近年、古い様式の楽器として評価が高まり、プロの演奏家や愛好者の間で再び注目されています。株式会社三創楽器製作所は、材料となる木材の選別、乾燥から、設計、部品加工、完成品組立までを全て手作業で一貫生産する日本で唯一のチェンバロメーカーで、音質にこだわり、メンテナンス性に優れたチェンバロの開発に取り組んでいます。
松尾正次氏(国本工業株式会社技監)

【専門分野】プレス金型によるパイプ加工
金属パイプを加工する際は、通常「ベンダーマシン」というパイプを曲げる専用の機械を使用しますが、国本工業株式会社では、一般のプレス機械と特殊の金型を使用して金属パイプを加工する独自の加工技術を開発しました。この技術を使うことで、「拡管」(パイプの径を拡げる)や「縮管」(パイプの径を小さくする)、「増肉」(パイプの厚さを厚くする)、「連続曲げ」(曲げと曲げの間の直線部分をなくす)など、ベンダーマシンでは不可能とされてきた加工が可能となりました。たとえば、拡管では元のパイプの直径を3倍に拡げたり、縮管は逆に3割にまで縮めたり、増肉は厚さを2倍にすることができます。このようにパイプを自由自在に変形させることができるため、自動車部品の設計においても自由度が大幅に向上したほか、これまで鋳造や薄板プレス成形、粉末成形等で作られていた部品をパイプ成形加工に置き換えることで、部品の歩留まり向上や軽量化、コスト削減に大きく貢献してきました。なかでも、「究極のパイプ加工」と称した燃焼式ヒーター排気パイプは、パイプの中に詰め物をせずにパイプの潰し成形を実現したことから、国立科学博物館に1年間展示されたこともあります。
平成25年度認定者
浅沼進氏(株式会社浅沼技研)

【専門分野】鋳造・計測分野
世界に通用するモノづくりをめざして、高い精度が要求されるエンジンやトランスミッション関連の試作品をアルミ砂型鋳造、機械加工、測定・検査までの一貫体制で製造しています。温度および湿度管理された工場の中で、100%人工砂を使用して造形した鋳型に溶けたアルミを流し込んで鋳造しています。また、新たな鋳造技術として、「新差圧鋳造法によるピンホールフリー技術」「チクソキャスティング法を活用したハイブリッドモールド」を開発しました。計測分野においては当社オリジナルの3次元測定機検証用ゲージ「クォリティーマスター」は、NIST(米国標準技術研究所)とトレーサビリティが取れており、この分野では日本初となるNVLAP認定校正事業者の資格を取得しています。さらに、「クォリティーマスター」はPTB(ドイツ標準研究所)ともトレーサビリティが取れています。
小原敏夫氏(株式会社ピアックス)

【専門分野】木工塗装(ポリエステル鏡面塗装)
ポリエステル鏡面塗装の特長は、平面の滑らかさとその輝き、手触りの重厚さです。鏡面仕上げは、材料の特質に合わせてポリエステル樹脂の塗膜の厚さを調節して吹き付けます。乾燥後、塗膜の厚さや硬さを見極めながらサンドペーパーの目の粗さを段階的に変えて磨きをかけていくと塗膜の表面の凹凸がなくなり鏡面のような光沢が生まれます。塗装の厚さがわずか0.3~0.5mm程度になるまで磨き上げます。この従来のピアノ鏡面塗装で培った技術を応用して特注家具やシステムキッチン等ピアノ以外の新しい領域に展開し、全国の家具メーカーや工務店、デザイナー等各方面から高い評価を得ています。特に技術的に難しいとされる5m程度の大きいものや円柱形など様々な曲面への鏡面仕上げを得意としています。
平成24年度認定者
神谷重久氏(元スズキ株式会社試作部試作技術課)

【専門分野】治具中ぐり盤作業
治具中ぐり盤(ジグボーラー)という精密加工機械を40年以上担当しています。この治具中ぐり盤を使って自動車やバイクの生産に欠かすことのできないマスターワークや工作物をきちんと正しい位置に固定することができる治具を製作しています。治具中ぐり盤は、とても剛性が高く精密な構造をしています。1/1000mm=1ミクロンというとても精度が高い加工が可能な機械で、ドリルなどで開けた下穴の内径を回転する刃物で削って広げていくことで正確な穴を削りだしていく機械です。基本の加工は穴あけですが、刃物が回転しながら上下前後左右に移動することができるので、溝加工や端面を削ることもできます。
竹本京司氏(株式会社タケモト専務取締役)

【専門分野】刃物等の特殊工具の試作製作と包丁研ぎ師
ピアノやギター、バイオリンなどの木製の楽器には、微妙な曲線があります。その複雑な曲面を持つところは手作業でしか加工することができません。楽器の形状に合わせたノミやカンナなどの特殊工具の試作・製作を行っています。また社寺の工事を手掛ける宮大工などの特殊な大工道具を製作しています。さらに、刃物の産地として有名な新潟県三条市や岐阜県関市などとのネットワークを持ち、量産対応できない少量多品種の特殊工具の開発を依頼されています。しかも、切れなくなった包丁やカツオ節削り器などを料理人や大工さんから依頼を受けて、研ぎ直して再び切れるように道具を再生しています。
山﨑肇氏(有限会社豊岡クラフト取締役会長)

【専門分野】木工製品の企画・開発・設計・製作
書見台、書類整理引出し、回転式ペン立て、名刺ケースなど机上に置く文具から、ジュエリーボックス、インテリア小物、マガジンラック、机やキャビネットなど小型家具まで、趣味性や意匠性、美術性の高い工芸品のような味わいを持つ高級木工製品を企画・開発・設計・製作しています。
平成23年度認定者
神谷武彦氏(神谷理研株式会社代表取締役社長)

【専門分野】表面処理加工(めっき技術)
金属の表面を滑らかにしたり、さびにくくしたり、光沢をもたせたり、硬くしたりと、内部とは異なった性質にすることを表面処理加工といいます。めっきは水銀に金を溶かした状態を表現した滅金(めっきん)が変化した日本語です。「めっき」とは、さびやすい金属の上にさびにくい金属を薄い膜で覆うことで、錆を防いだり、美観を保つ表面処理加工の方法です。亜鉛メッキは錆を防ぐ防蝕(ぼうしょく)に、クロムメッキは表面の硬化と美観の維持によく使われています。また、光沢を保つためや鏡のような機能を持たせるためにプラスチック樹脂にめっきをすることもあります。このほかにも、潤滑と放熱のためにエンジン部品に銀をめっきすることもあります。また電子部品の殆どにメッキが施されています。プリント基板へのスルホールメッキ、シリコンウエハーへのメッキ、接点や端子部品への金、銀、錫メッキ、ハードディスクへの無電解ニッケルメッキ、LED素子を搭載する部分への銀メッキ、その他数え上げればきりがありません。また、ガラスやゴム、チタン、マグネシウム、砂など、簡単にめっきできないものにめっきすることにも取り組んでいます。
古橋敏明氏(古橋織布有限会社取締役)

【専門分野】テキスタイル(織物、布地)の製造・販売
古くから綿織物の産地として栄えた浜松地域において、平織の旧型シャトル織機を使いこなし、素材を活かす伝統的な手法にこだわった独自のテキスタイルの開発、製造、販売を手がけています。従来の織物よりも糸密度を高くした緻密な織物は、毎年積極的に出展している展示会で興味を持ったバイヤーやデザイナーが、製造の現場を目で確かめにくることもあります。浜松の工場まで足を運んで、その場で商談が始まったりすることも多く、取引が広がっています。また、国内だけでなく、海外の展示会に出展したり、ミラノ在住の日本人エージェントを介して布地をプレゼンするなどして、ヨーロッパなど海外からも注目を集めています。
増田久雄氏(株式会社増田酸素工業所取締役会長)

【専門分野】金属及びそれらに付帯する接合技術
溶接は、鉄などの2つの金属を溶かしてつなげる技術です。船舶や自動車のボディ、トラックやバイクのフレームなど溶接の使われる領域は幅広く、航空宇宙や橋梁、高層建築にも使われています。母材の金属を溶かす方法としてアセチレンなどの可燃性ガスを燃焼させるガス溶接と、電気を流して溶かすアーク溶接などがあります。また、最近では光ビームを使ったレーザー溶接なども使われています。金属の中には、空気中の酸素と結合して金属の表面に薄い酸化被膜を形成するものがあります。この酸化被膜が生じると金属同士がうまく溶け合わずに溶接がうまくいかないことがあります。非常に軽量で丈夫な金属であるチタンは、大気との親和性が強く酸化被膜を形成するのが非常に早く溶接するには難しい材料です。研究した結果、溶接が難しいチタンも溶接ができるようになりました。軽量で機能的な素材の溶接加工が可能になったことで、応用範囲が広がりました。
毛利俊甫氏(株式会社ポリシス代表取締役)

【専門分野】ウレタン樹脂の用途開発
アルコールと石油化学製品のイソシアネートを混ぜ合わせて反応させると、ポリウレタン樹脂が出来上がります。アルコールのことをポリオールといいますが、ポリオールには何千種もあり、イソシアネートと組合わせてどのポリオールを混合するかで出来上がるポリウレタンの樹脂の性質が変わってきます。堅いものから柔軟性に富むものまで、粘着性を持ったものから振動吸収性に富んだものまで、さまざまな機能を備えたウレタン樹脂が生み出されます。これまで、医療用のトレーニングに使う注射の訓練用皮膚とか、切開や縫合の練習に使う人造皮膚、また手術用のシミュレーションに役立つ臓器の製造をしてきました。このほかにも、空気中の水分を吸収して硬度が増していく塗料などから振動を吸収する性質を持ったクッションなど、またお湯で自在に変形して常温で硬くなる粘土や形状記憶樹脂も開発しました。お客様のニーズを受けて、要求される機能を備えたポリウレタン樹脂を開発して原料として提供しています。
平成22年度認定者
高柳眞氏(株式会社TRINC代表取締役会長)

【専門分野】静電気とクリーン関連技術
私たちが普段暮らしている中で、静電気の発生が問題となることがあります。ものづくりの現場で、扱うプラスチック製品などは、その製造の途中で静電気を帯びやすく、その静電気によってごみを吸着することが多くあります。自動車用の樹脂バンパーの塗装工程では、静電気を帯びたバンパーがホコリを付着したまま塗装されるだけで不良品になってしまいます。このやっかいな静電気を除去することでホコリが付着しないようにする技術を開発しました。いろんな業種で静電気の問題が起きています。この技術は、塗装ブースやフィルムの加工工場で、印刷分野で、また電子機器組立など、幅広い分野で静電気を除去することに役立っています。相談を受けた課題には「実証主義」を掲げて、はっきりと効果があることにこだわっています。課題解決に取り組んだ現場では、不良の発生を劇的に下げるなど、大きな効果を上げています。
西尾眞之氏(西尾精密株式会社相談役)(故人)

【専門分野】塑性加工(冷間鍛造:線材の圧造成形に関する金型の設計・製作・調整および生産技術)
塑性加工(そせいかこう)とは、材料に大きな力を加えて変形させることで、ねじやさまざまな部品の形を作り出すことです。複数の金型を使って、硬い鉄を曲げたり、絞ったり、膨らませたりと何段階か変形させる工程を経て、複雑な形状の部品を作り出します。一般に他の加工法よりも加工時間が短く、材料に無駄の出ない素形材造形技術です。
福地三則氏(ロボ・スタディ株式会社代表取締役社長)

【専門分野】スマートフォン用アプリケーションソフト開発
スマートフォンの登場で、これまでの情報環境が大きく変化することが期待されています。教育用アプリケーションを開発していますが、これまでの19年間にわたり、パソコンや任天堂DS向けに作り続けてきたコンテンツにはかなりの蓄積を持っています。この豊富な蓄積をもとに2009年12月に発売した教育アプリ「英単完全攻略8000語」は、Xmasの朝にAppStoreで1日の売り上げ本数がNo.1を記録。翌年発売したリスニング訓練アプリ「えいご上手」は総合1位を獲得。2010年のAppStore殿堂入りアプリに選定されました。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください