緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年3月11日
年代別健康づくりの目標
乳幼児・学童期(1~12歳)
基本的な考え方
乳幼児・学童期は、家庭において子どもの健康づくりを進め、基本的な生活習慣を確立する時期です。保護者が地域とつながりを持ちながら安心して子育てができる環境を社会全体でつくる必要があります。
市民のやらまいか
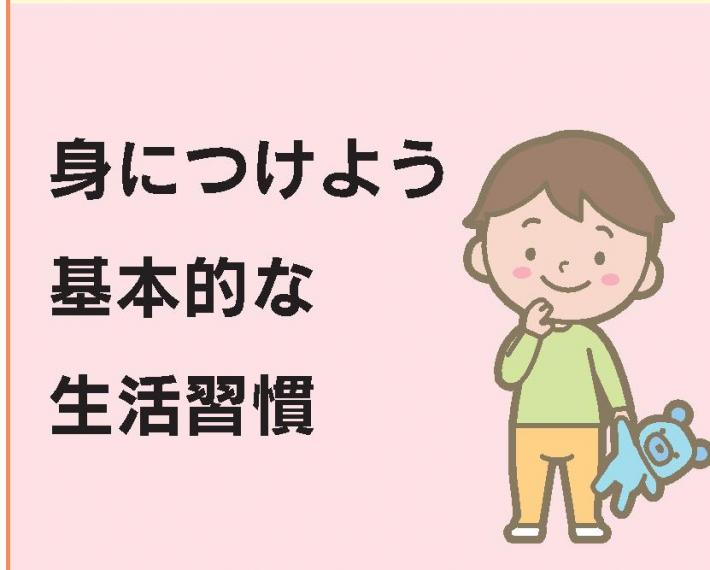
- 早寝・早起きをする
- 朝食を必ず食べる
- 主食・副菜・主菜をそろえて食べる
- 減塩を心がける
- 外で楽しく遊ぶ
- 家族や仲間と話をする
- フッ素入り歯みがき剤を使って歯をみがく
思春期(13~19歳)
基本的な考え方
思春期は、身体の成長や人間関係の広がりなどにより、心身ともに大きく変化する時期です。また、命の大切さや正しい性の知識を身につける時期でもあります。家庭や学校、地域と連携しつつ、次世代を担う健やかな子どもの育成を進めていくとともに、子ども自身の健康づくりに対する意識を高め、主体的な健康づくりを進めていけるよう支援することが重要です。
市民のやらまいか

- 自分から気軽にあいさつをする
- 朝食を必ず食べる
- 主食・副菜・主菜をそろえて食べる
- 減塩を心がける
- 悩み事を相談できる相手を持つ
- 酒・たばこ・薬物に手を出さない
- フッ素入り歯みがき剤や糸つきようじ等を使って歯をみがく
- 性感染症の予防について正しい知識を身につける
青年期・壮年期(20~44歳)
基本的な考え方
青年期・壮年期は、就職や家庭を持つなど、ライフスタイルがめまぐるしく変化する時期です。長期的な目線で健康づくりを進めるためにも、食生活や運動、飲酒などの望ましい生活習慣を定着させていくことが重要となります。
市民のやらまいか

- 健診(医科・歯科)を定期的に受ける
- 朝食を必ず食べる
- 主食・副菜・主菜をそろえて食べる
- 減塩を心がける
- 意識的に今より10分多く体を動かす
- 悩み事を相談できる相手を持つ
- 質の良い睡眠を心がける
- たばこは吸わない
- 適量適酒、休肝日をつくる
中年期(45~64歳)
基本的な考え方
中年期は、加齢による身体機能の低下などにより、生活習慣病などの病気が発症しやすい時期です。運動の習慣化など、自主的に健康づくりを継続する必要があります。また、社会的役割も大きくなっていることから、ストレス解消法を持つなど、こころの健康づくりも重視する必要があります。
市民のやらまいか
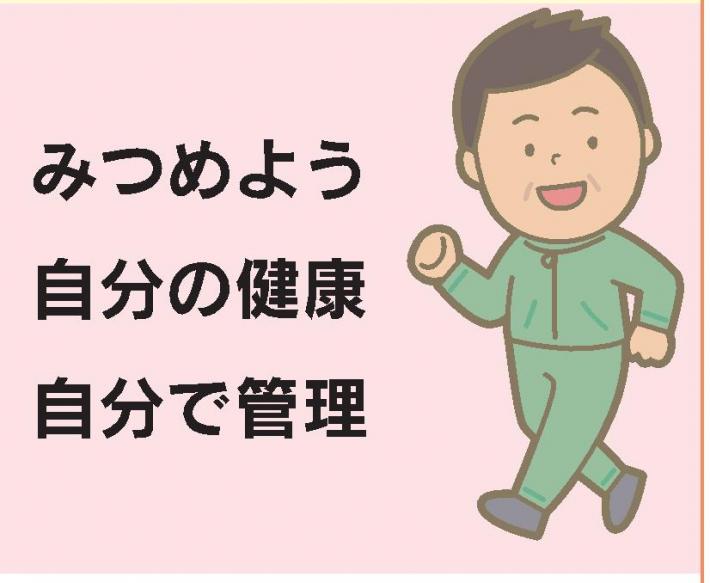
- 検診(医科・歯科)を定期的に受ける
- 毎日、体重計にのる
- 主食・副菜・主菜をそろえて食べる
- 減塩を心がける
- 意識的に今より10分多く体を動かす
- 自分に合ったストレス対処法を持つ
- 質の良い睡眠を心がける
- たばこは吸わない
- 適量適酒、休肝日をつくる
高齢期1(65~74歳)
基本的な考え方
高齢期1は、仕事や子育てを終え、「個人の生活の質」の向上がより重要となる時期です。認知症や寝たきりにならず自立した生活を送ることができるよう、一人ひとりの健康に対する意識を高めていく必要があります。また、生活環境の変化や、自身の健康状態の悪化などから、うつ病にかかりやすくなる時期でもあります。生きがいを持ちながら生活するため、ボランティア活動などを通じ、地域のつながりを深めることが大変重要になります。
市民のやらまいか
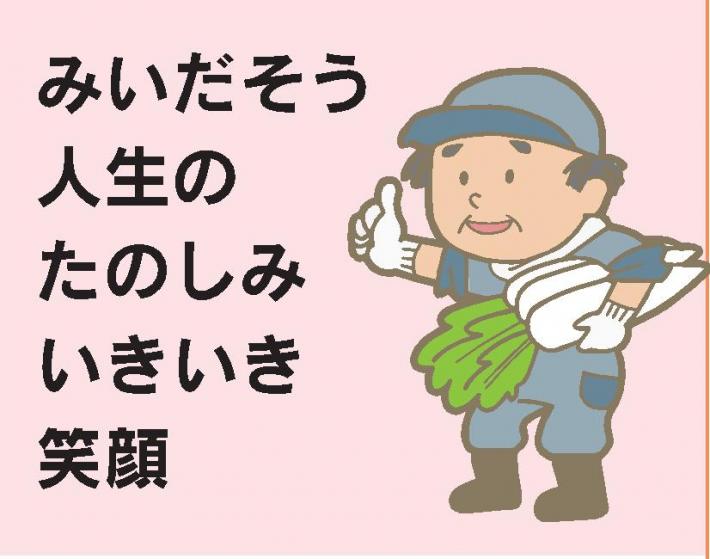
- 趣味や生きがいを持つ
- ボランティア活動に参加する
- 健診(医科・歯科)を定期的に受ける
- 主食・副菜・主菜をそろえて、1日3食しっかり食べる
- 減塩を心がける
- 体力に合った運動・スポーツを楽しむ
- 自分の口に合った歯のみがき方を身につける
高齢期2(75歳以上)
基本的な考え方
高齢期2は、一人ひとりの健康に対する意識を高めるだけでなく生活環境の変化や、自身の健康状態の悪化などから喪失感が強くなるため、趣味や生きがいを持つことや外出機会を増やし人とのつながりを深めることが大切です。
市民のやらまいか
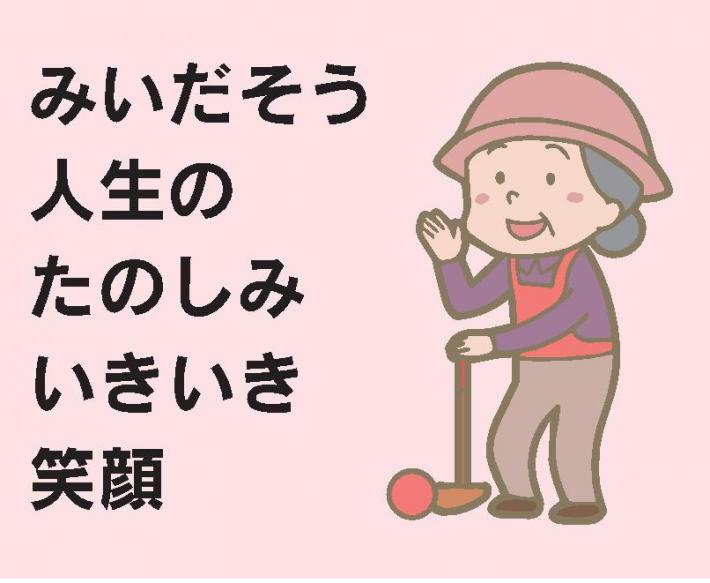
- 地域活動(自治会、シニアクラブなど)に積極的に参加する
- 趣味や生きがいを持つ
- 健診(医科・歯科)を定期的に受ける
- 主食・副菜・主菜をそろえて、1日3食しっかり食べる
- 減塩を心がける
- 外出する機会を増やす
- よく笑い、よくしゃべる
- 1日1回自分の歯と口を見る
健康はままつ21 詳細な情報
概要
分野別施策
年代別健康づくりの目標
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください