川廷さんとともに学ぶ 未来を変える浜松のSDGs/【対談記事】れんりの子(愛管株式会社)

今回訪れたのは、浜松市浜名区都田町にある認可保育園「れんりの子」。配管工事やレストラン、農園など、多岐にわたる事業を手がける愛管株式会社が運営し、未来の環境リーダーを育成しています。
れんりの子は、特定非営利活動法人 幼年教育・子育て支援推進機構の食育コンテストで優秀賞を受賞するなど、浜松だけでなく、多くの地域からも注目を集める保育園です。愛管株式会社代表取締役の中村将義さんとれんりの子園長の富田知可子さんから、取り組みの背景や課題についてお話を伺いました。
【SDGs達成に向けた取組のポイント】
- 食農保育では、作物の管理から収穫、食事を通じて園児のSDGsの体験や理解を促進している。
- 園内の遊具や門扉等に配管工事の廃材をリサイクルして使用することにより、資源の有効活用と園児へのSDGs教育に繋げている。
- 園児のSDGsの学びが保護者の学びや人材確保にも繋がっており、波及効果が高い取組になっている。
保育園から始まる「幸せの好循環」が、浜松から世界に広がる
縁を引き寄せ、夢を叶える言葉の力
川廷昌弘さん(以下、川廷):最初に、保育園の運営元である愛管について教えていただけますか?
中村将義さん(以下、中村):愛管は、1983年(昭和58年)に私の⽗が創業しました。⽗は、株式会社稲徳⼯業所(配管業)に新卒で⼊社し、4年ほど現場監督を務めていました。その後、佐鳴台で建築屋さんと共同で喫茶店(ヒコウビラン)を経営し始めました。経営が順調になると、次に何かを始めようと考え、かつて勤めていて⼈脈もあり、仕事内容を把握している配管業が良いと考えました。地元の元気な若者を集め、スコップ⼀つで配管業を始めたと聞いています。

愛管株式会社の代表取締役である中村将義さん
川廷:中村さんが事業を引き継がれて5年がたち、愛管はレストランや農園、幼稚園など、さまざまな事業を展開されていますね。
中村:長い間、土地を借りて事業を営んでいましたが、信用金庫の紹介で土地を譲っていただき、レストランを開業したのが多角化のスタートです。その後、さまざまなご縁があり、レストラン北側の農園のほか、周辺の工場や農地を譲っていただきました。保育園は借地ですが、現在は約6000坪の敷地で事業を行っています。

園舎は、管工事の廃材を活用する以外にも、木のぬくもりが感じられるように建てられており、子どもたちが遊び、過ごしやすい工夫が随所にされている。
川廷:保育園事業を始めたのはなぜですか?
中村:私はひとり親で、父と祖父と祖母に育てられました。お寺が運営する保育園に通っていて、お寺のご家族とともに成長したと言ってもいいほど、とても楽しい時間を過ごすことができました。あの時間がなかったら、きっとグレていたはずです(笑)。この体験を多くの人に伝えたいと思い、父に保育園事業の提案をしたところ、初めて「いいじゃないか」と言ってくれました。
偶然にも、敷地の隣に保育園の設計を専門とする設計士がいらっしゃいました。農園があり、レストランなどを併設するこの環境が、保育園の一番の魅力になると感じていました。調整区域にあるため農業しかできなかったのですが、それを逆手にとって、農業ができる保育園を立ち上げたいと考え、設計士から富田を紹介していただきました。
富田知可子さん(以下、富田):以前は、幼稚園の先生のほかに、ママのための子育て支援サークルを主宰したり、大学で教えたりしていました。声をかけていただいたのは、ちょうど子育てが一段落したタイミング。一緒に敷地を見て、ここでなら私が理想とする保育が実現できるかもしれないと感じ、中村の話にも共感する部分も多く、一緒に保育園を始めることを決めました。

れんりの子の園長を務める富田知可子さん
中村:子ども農園を作っていただいたり、情報発信をしてくれたり、まだ3年ですが全国で表彰される保育園になりました。この「れんりの子」から育っていく子どもたちが、きっと社会の礎になってくれると思っています。
川廷:中村さんご自身で道を切り拓いたからこそ、このようなご縁を引き寄せたのですね。ご縁は座って待っていても手に入れられるものではなく、「私はこれがしたい」と発信していくことが大事ですよね。
中村:そうですね。言葉に出さなければ、思いは伝わりませんから。農業を通じて保育をしたいという思いを語り、富田と出会えました。富田も自身の理想とする保育の在り方を表現し、発信してきました。その中で、SDGsというのが、お互いのやりたいことの指標になるのではないかと感じました。
日々の一つひとつの活動が、SDGsにつながっていた
川廷:保育園にSDGsをどのように活用していますか?
富田:最初に中村から言われたとき、保育園でできることはないと思っていました。「子どもたちができることなんて、残さず食べるとか、ゴミを捨てないといったことぐらいですよ」と伝えたら、「それでいい」と言われました。改めて保育園でしている活動を書き出してみたら、食農保育は「12つくる責任、つかう責任」「15陸の豊かさも守ろう」など、地域交流では「11住み続けられるまちづくりを」など、SDGsに当てはまることがいろいろあることに気づきました。

敷地内には、子供たちが自ら育てる農園がある
富田:普段何気なくしている活動が、全てSDGsにつながっているという話を子どもたちにすると、彼らも少しずつ意識し始めて、自分はこれくらいなら食べられる、食べられない分は食べられる子にあげるなどの行動を取り始め、今では残食がほぼゼロになりました。
川廷:素晴らしいですね。



保育園にある子ども農園で育てた野菜を収穫し、園で食べる。余った野菜は愛管本社やレストランなどにおすそわけ。喜んでもらいたいからと、子どもたちが野菜をきれいに磨く
富田:いつもしている活動がSDGsの取組みで、こんなに小さな保育園が、世界のためにできることはないと思っていましたが、浜松を住みやすくすることがSDGsにつながるのなら、自信を持って「SDGsを実践している」と言うことができます。
川廷:親御さんの反応はいかがですか?
富田:待機児童の問題もありましたので、最初は保育園に入れればどこでもいいという考えの方が多かったのですが、最近は、少しずつ変化しているように感じています。子どもたちは、保育園で育てた野菜を家でも食べたいので、保護者の方に「給食で食べた大根とカツオと梅をあえたのを作って」と言うようで、園に「レシピを教えてください」と言う親御さんが増えました。園の食事では、だしも取っていますので、親御さんもだしを取るようになったと聞きます。子どもたちの影響力は非常に大きく、親の考え方や行動にも変化が生まれています。



余った配管を再活用し、職人が作ったブランコや鉄棒、フラフープなどの遊具が人気
川廷:親子の関係にも好循環が生まれていますね。自然に触れることでの子どもたちへの影響はどうですか?
富田:保育園の農園は農薬を使っていないので虫が来ますが、その虫を捕るのも子どもたちの仕事です。みんな集中して、静かに虫を捕ります。そういった作業の集中の積み重ねがあるので、人の話を聞くときはちゃんと集中して聞くことができます。先日も、近所の図書館に行った際には、マナーが守られていてすごいですねという言葉をいただきました。

ブルーベリーやミカンを守るためにみんなで協力して虫を捕まえる
川廷:SDGsというと、貧困や環境問題を考えることが大事と思われがちですが、一番大切なのは「人間開発(Human Development)」。これがSDGsの根幹です。
「人間開発」とは、「自分はこう生きたい」「こんなことをしたい」など、自分の意思に基づいて選択できる社会のこと。この社会は誰かに作ってもらうのではなく、自分が行動することで誰かに影響を与えたり、反対に、行動する他者を見て、自分も何か行動を起こしたりする好循環が社会そのものだと言えます。みんなが好循環を与え合う状態を作ることが、SDGsが目指す本当のゴールです。
人を育てる。地域が変わる
中村:「好循環」という言葉は、この保育園の理念にもあります。「愛情をたっぷり受け、信頼できる環境で育った子どもたちは、周りの大人たちを成長させる」という育て合いの好循環を生み出し、情緒の安定、保護者の心のゆとり、地域社会への貢献へとつながっていきます。
川廷:まさに人間開発ですね。根本にそのような考え方があるからこそ、園の活動がSDGsにつながり、人や社会、地域と結びついていくんですね。
中村:はい。人だけでなく、パイプもつなげていますが(笑)。好循環という言葉と出会ったのは、父が亡くなり、愛管の経営理念を作らなければならなくなったタイミングでした。最初に知ったのは生態系の話で、食物連鎖がうまく回ると自然環境が保たれるといった内容でした。好循環ってとても良い言葉だなと思い、それをどう生活に組み入れられるか考えていると、「暮らし(Life)」という言葉が浮かび、「幸せの好循環」という愛管の経営理念につながりました。
川廷:それは、らせんのように上昇していく感じでしょうか。
中村:まさにそうです。「Life Spiral Up」と名刺にも入れています。
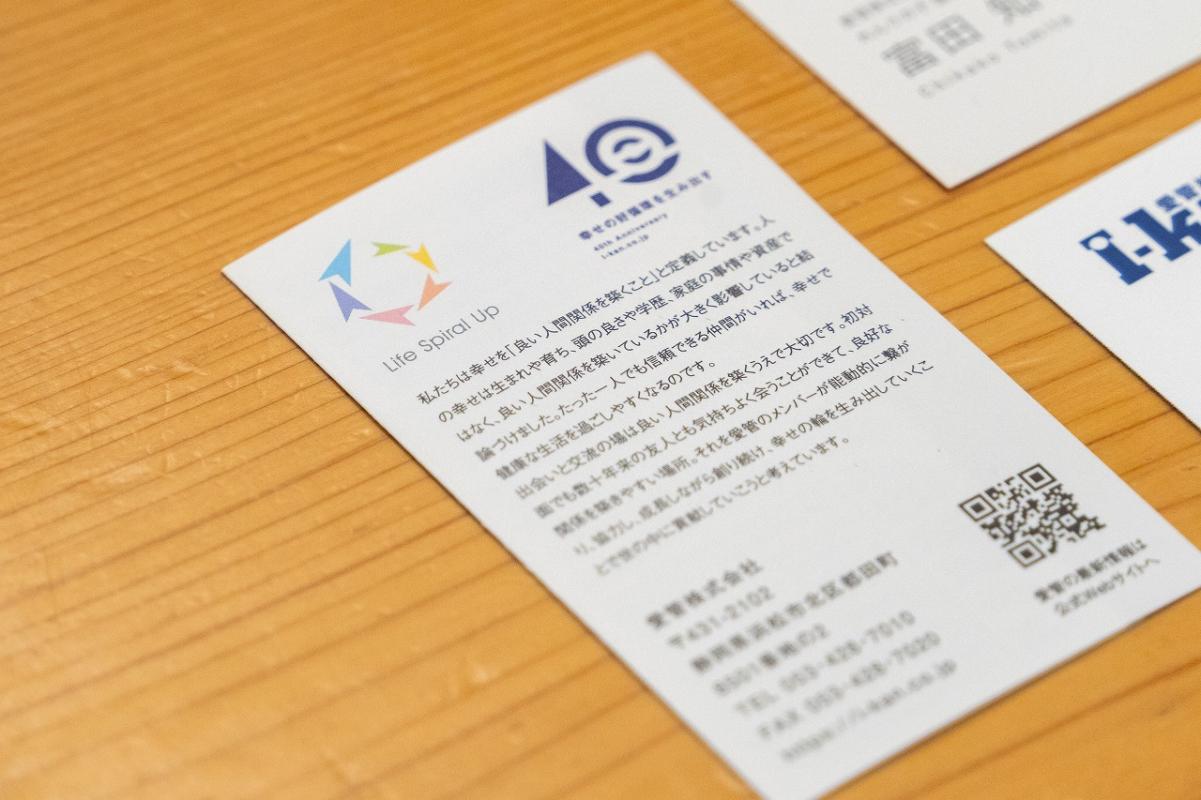
愛管の名刺の裏には経営理念とともに「Life Spiral Up」のロゴが印刷されている
川廷:経済成長では、人が経済を成長させるための道具として扱われますが、本来は人が幸せになるために経済があるもの。考え方、価値観が逆なんですね。そのため、SDGsでは経済成長は人が幸せになるためのツールだという考え方がなされています。
中村:ハーバード大学が幸福と健康の調査を行い、人の幸せは生まれや育ち、頭の良さや学歴、家庭の事情や資産ではなく、「良い人間関係」を築いているかが大きく影響していると結論づけました。孤独では幸せになれませんが、信頼できる仲間がひとりでもいれば、幸せになれると言っています。
私は、「暮らしの好循環」や「幸せの好循環」というものを進めていかなければならないと考えています。それが地域社会の発展や、浜松の成長につながってくれたら、こんなにもうれしいことはありません。
そして、実際にこうした会社の理念に賛同し、東京などから浜松市に移住して働いてくれる若者も出てきています。今日一緒に来ている八巻もその一人です。

まわりも幸せにするという理念に共感して、東京から移住したスタッフの八巻さん。
川廷:SDGsの本質的なところは、好循環をつくっていくことです。「つながり」も大事なワードであり、17のゴールもばらばらではなく、良い循環で他のゴールにつながります。つながりを生み、ローカライズ(地域ごと化、自社ごと化)を進めるために169のターゲットのつながりもぜひ見てほしいですね。

保育園の活動は近くにある図書館でも展示。地域に開かれたさまざまな取り組みが行われている
川廷:次世代の育成は、喫緊の課題です。SDGsでも本当に大切なのは、「4質の高い教育をみんなに」だと言われています。保育園事業を通じ次世代をちゃんと育成し、未来づくりに資する、わんぱくで、お行儀のいい子どもたちを育てていることを、もっと自慢してもいいと思います(笑)
中村:例えば、単に「食育」という取組の表面だけだと、どの取組も同じに見えてしまいますが、SDGsが経営理念や自分たちの取組の振り返りにつながったと感じています
川廷:まずは、世界の問題ではなく、自分たちの問題として取り組むことが重要です。自分たちの足元から始めることが、地域、日本、世界へと広がっていきます。浜松の地域課題を解決できるのは、遠く離れた、例えばアフリカの方々ではなく、浜松に住んでいる人間です。動機や理由である「なぜ」が本質的に大事で、その地域の人しかできない取り組みこそが、SDGsそのものなんです。
今日はありがとうございました。

(まとめ)
SDGsを実践するには、表面的な取り組みではなく、動機が非常に重要です。自分の身の丈や状況にあった活動を行っているからこそ、心に響くお話を聞くことができました。素晴らしい環境に囲まれ、おふたりをはじめ、思いのあるスタッフが集い活動しているからこそ、親御さんを巻き込み、主体的な子どもたちが育っているんだと感じました。まさに、小さな社会をつくっていると言えます。この保育園の取り組みが、浜松だけでなく、より多くの地域に広がっていくこと楽しみにしています(川廷)
|
愛管株式会社 「Life Spiral Up 浜松から幸せの好循環を生み出す」を経営理念とし、水でつなげる街づくりと社会貢献を主軸に、配管工事や飲食事業、保育事業、グランピング施設など、多くの笑顔を作り出すための事業を行う。 https://i-kan.co.jp(別ウィンドウが開きます)
れんりの子(認可保育園) 2021年4月の開園以来、保育方針に『食農保育を通して「共に生きる力を育む」』を掲げている。園舎に併設された「こどものうえん」では、園児が自ら作物を育てて収穫し、給食での食材利用や自ら調理して食べるという体験を通じて旬の食べ物や地域の食文化に触れる取組をしている。また、園児たちに対し、株式会社愛管の管工事業で出た廃材を利用した遊具や看板、フェンス等を通じてリサイクルの重要性を教えたり、地中熱を活用するビニールハウスを通じて環境に優しいエネルギー利用を教えたりしている。こうした教育活動は、地域社会にも広がり始めている。 |
| 関連リンク |

