緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年9月26日
浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針11
2 道路施設ユニバーサルデザイン指針策定
(2)対象施設・項目 2)歩道 歩道構造<歩道構造>
○基本的な考え方
自動車と歩行者等の通行帯を分離し、歩行者等の安全を確保するだけでなく、車いす使用者や高齢者を含めたすべての人に配慮し、路面が連続して平坦となるような構造とします。
○整備指針
(1)歩道を新設する場合の構造形式はセミフラット型を標準とする。
(2)歩道等の車道等に対する高さは、5cmとする。
歩道構造形式の種類と定義
|
歩道構造形式 |
定義・特徴 |
|---|---|
|
フラット型 |
歩道等面と車道等面の高さが同一で、縁石により歩道と車道を分離する歩道構造。 |
|
連続した平坦性が確保できるが、視覚障がい者にとって歩車道境界が認識しづらいことや、路面排水が車道から歩道に流入する欠点がある。 |
|
|
セミフラット型 |
歩道等面が車道等面より高く、縁石天端の高さが歩道等面より高い歩道構造。 |
|
横断歩道部に段差0cmの縁石を使用することにより連続した平坦性が確保でき、歩車道境界の認識も可能である。 |
|
|
マウントアップ型 |
歩道等面と縁石天端の高さが同一である歩道構造 |
|
明確な歩車道境界の分離が可能であるが、車両乗入れ部や横断歩道接続部等ですり付けが必要となるため、連続した平坦性が確保出来ないという欠点がある。 |
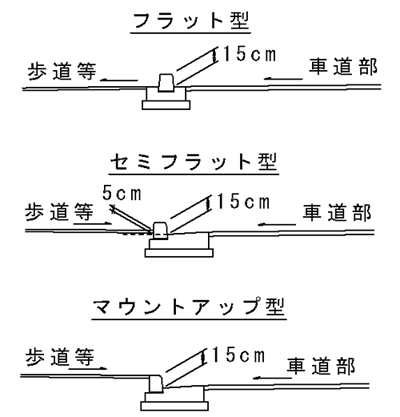
(3)現状の歩道構造形式がマウントアップ型、フラット型である場合の、標準歩道高さ5cmの整備方法は以下に従うものとする。
現状がマウントアップ型
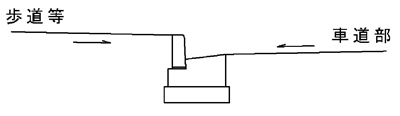
↓
路肩の勾配、車道の勾配が変更可能か?
↓
Yes
車道の勾配を逆勾配とする
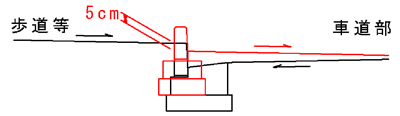
車道の高さ変更が可能か?
↓
Yes
車道の高さを上げる
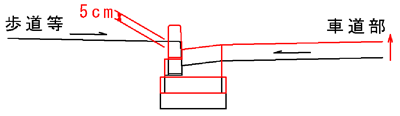
民地側における歩道高さとの調整が可能か?
↓
Yes
歩道等の高さを下げる
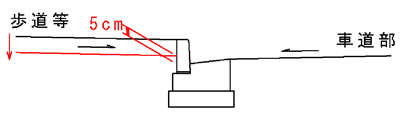
現状マウントアップ方とし、車両乗入れ部、横断歩道接続部、
取り合い道路部において適切なすり付け処理を行う(次項参照)
現状がフラット型
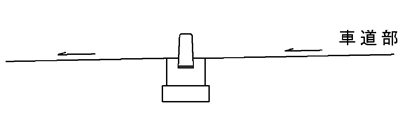
↓
路肩の勾配、車道の勾配が変更可能か?
↓
Yes
路肩の勾配を変更する
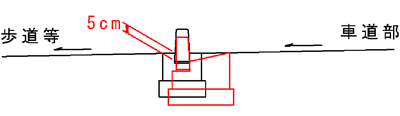
車道の高さ変更が可能か?
↓
Yes
車道の高さを下げる
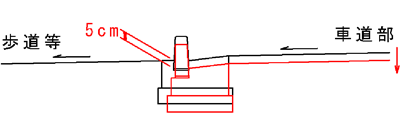
民地側における歩道高さとの調整が可能か?
↓
Yes
歩道等の高さを上げる
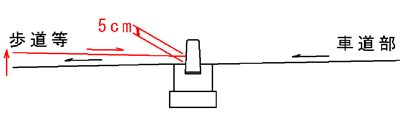
現状フラット型とする
(4)やむを得ずマウントアップ形式とした場合、各部すり付け処理は横断勾配10%以下、縦断勾配5%以下で行う。
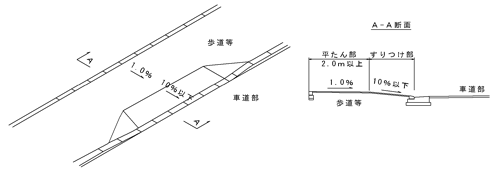
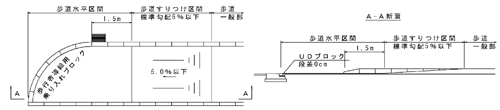
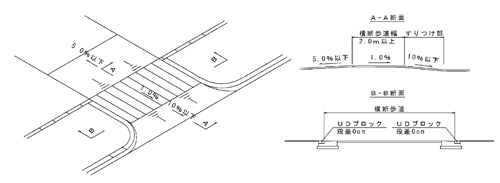
○整備水準
- 原則として市全域で適用する。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください