緊急情報
サイト内を検索
ここから本文です。
更新日:2023年6月21日
第5回 区版避難行動計画策定会議(南区)
※会議資料は、地図や写真が入っているためサイズが大きいものがありますので、ご注意ください
次第
~冊子と防災マップを最終確認し、今後の活用方法について考えよう~
- はじめに
- 本日の内容確認
- 避難行動計画と防災マップについて 資料1(PDF:136KB)、資料2-1(PDF:8,711KB)、資料2-2(PDF:409KB)
- 前回出された意見の振り返り
- 避難行動計画と防災マップの最終確認
- 避難行動計画などの今後の活用について 資料3(PDF:40KB)
- 避難行動計画と防災マップを活用してもらうために、地域でできることを検討
- 感想
- 全5回の策定会議を終えた感想や今後の地域における防災活動について
要旨
【日時】 平成24年10月12日(金曜日)午後2時~午後4時20分
【場所】 南区役所
1. 概要・要旨
- 避難行動計画の冊子内容の最終確認
- 防災マップの体裁と掲載項目の最終確認
- 今後の活用方法の検討
2. 決定した事項
[1]避難行動計画の冊子の内容について
- 避難行動計画冊子の掲載内容について確認
- 本日の意見を踏まえて修正を行った冊子を委員へ郵送し、最終確認とする
- 冊子に掲載できない事項については、別途作成している詳細版に掲載することを確認
[2]表紙で呼びかける内容について
- 表紙の内容について以下の4案で比較検討を行った。挙手による投票の結果、南区としては「事前に備えること」を強調するウ案もしくはエ案を推す。最終決定については事務局に一任 ○「この冊子で行う3つのこと」
(挙手による投票)- ア従来の文言通り 0票
- イ1番目を「我が家の避難行動を考える」に変更 1票
- ウ従来の文言+欄外に「事前に備えること」の文言を挿入 3票
- エ上記イ+欄外に「事前に備えること」の文言を挿入 3票
3. 指摘・確認事項
[1]避難行動計画の冊子の内容について
- 委員より出された意見を踏まえ、冊子の最終校正を行う
【意見要旨】
- 全体に関わること
- 図中の「天竜川」などの縦に伸びる河川の名称は縦書きとする
- 表紙のデザイン
- 保存版の位置、「浜松市 平成25年3月」の文字の大きさなどは、全区の意見を踏まえ、最終的に文字バランスなどを調整する
- 災害特性
- 地図の海抜0m~2m、4m~6mの色が似ており、判別がしづらいので修正する
- 図中の「昭和20年破堤箇所」の下に「安間川」の表記があるが、破堤したのは当時の天竜川西派川であり、その旨を記載する
- 地震・津波
- 地震・津波の避難行動のポイントの「合言葉」を「地震だ 津波だ すぐ逃げろ」に変更する
- 津波の浸水想定図について、位置の判別がつきやすいよう、地名の入った前回提示の地図に戻す
- 震度は東海地震の想定図、津波の浸水は南海トラフ巨大地震の想定図と、それぞれ現時点で得られる最新の情報を掲載するが、来年度県が第4次被害想定を発表後に両者の改訂版を作成する予定とする
- 液状化については、例えば東日本大震災時の千葉県の舞浜と南区では地盤条件が異なると思われるので、被害写真などの掲載は控え、起こる被害のイメージをイラストや文章で記載することとする
- 液状化については、東海地震まで至らない震度の場合でも発生の危険性があることを追記する
- 風水害
- 台風時などの停電の際の心構えについて、風水害の避難行動のページへの掲載を検討する
- 天竜川のはん濫の想定は、平成19年に発行された洪水ハザードマップを掲載する
- 市指定避難所
- 県立高校は、市の避難所が一杯となったときの予備避難所となっており、指定避難所としては位置づけない。なお、高校は津波避難ビルには指定されており、位置は防災マップにて確認できるようにする
- 可美小学校、飯田小学校に避難所のマークが抜けているので追加する
- 情報を得る
- 「停電に備えて」のラジオのイラストに、「充電できるものを」の文言を追記する
- いざというとき役立つ知識
- 「地震時にけがをした時は・・・」の欄に、クラッシュ症候群についての知識と対応方法の記載を検討する
[2]防災マップについて
- 河輪地区、芳川地区のラインが一部間違っているので再確認する
- 冊子の1ページ、2ページで名前が出てくる寺社については、掲載したほうが良い
- 各地区とも地区の周りに余裕がある図郭となっており、1枚で活用できる
4. 今後の活用について
- 以下のように意見交換を行い、今後の課題とした
|
主体 |
いつ |
どのように使うか |
必要な行政支援 |
|---|---|---|---|
|
自主防災隊 |
|
中心となって活用する |
|
|
自治会 |
|
テキストとしてワークショップを行う |
|
|
|
リーダーを養成する |
|
|
|
ありとあらゆる機会をとらえて |
活用の機会を設ける |
|
|
|
自治会 (サロンのような小さな単位で) |
|
防災カードづくり、マップづくりの出前講座を行う |
|
|
自治会 (集会所に入る人員の単位で) |
|
活用の機会を設ける |
|
|
学校 |
|
生徒に宿題として考えてもらう |
|
|
学校(親子で) |
|
避難場所へ歩いてみる |
|
|
学校 PTA |
年度計画にいれてもらう |
テキストとして勉強会を行う |
|
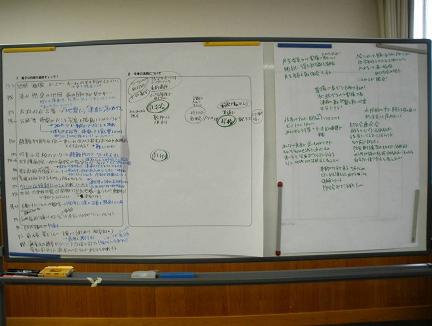
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください