緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年1月4日
地質の日協賛 テーマ展「浜松の災害史」
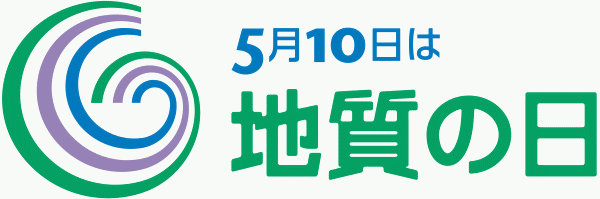
2011年3月11日に発生した「東日本大震災」以降、人々の防災に対する意識や関心が高まってきています。また、過去の地震や津波の記録に対しても、見直しがされるようになってきました。浜松市博物館では近い将来発生すると考えられる東海大地震をふまえ浜松周辺で過去に発生した災害を記録した文書や絵図をご紹介いたします。昔の人々は被災したときどのように対応していったのか、また現在お住まいの地域がどうなったのか、ご来館された皆様にお考えいただきたいと思います。
開催概要
|
開催期間 |
平成24年4月14日(土曜日)~平成24年6月3日(日曜日) |
|---|---|
|
開催場所 |
浜松市博物館 特別展示室 |
|
開館時間 |
午前9時~午後5時 |
主な展示物
![[画像]舞阪宿津波図](/images/9536/image4_1.jpg)
舞坂宿津波図
江戸時代末
安政大地震の津波の様子を描く
![[画像]天竜川下流御普請絵図](/images/9536/image5_1.jpg)
天竜川下流御普請絵図
文化12年
![[画像]変化抄](/images/9536/image6_1.jpg)
変化抄
竹村広蔭著
江戸時代末
安政大地震の記事あり
地質の日について
明治9年(1876)、当時の政府が招いていたアメリカ人の地質学者ライマン(B.S.Lyman 1835-1920)によって、日本で初めての地質図「日本蝦夷地質要略之図」が5月10日に刊行されました。文部科学省は平成20年よりこの日を「地質の日」と定め、地質学会や古生物学会、全国の博物館などで同時開催事業を展開しています。
浜松市は中央構造線が縦断し、ナウマンゾウの模式標本が発見されるなど、地質学でも注目されている土地です。博物館本館でナウマンゾウ化石を、姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館でも浜名区細江町内出土ナウマンゾウ化石を、天竜区にある水窪民俗資料館で中央構造線にかかわる岩石標本や化石をご紹介しています。

浜松市ゆかりのナウマンゾウ
かつて、浜松市中央区佐浜町の浜名湖畔で見つかった新種の象化石が模式標本となって、「ナウマンゾウ」という新種の象が認定されました。市内でも各所で化石が見つかっている、日本を代表する化石象です。浜松にも数万年前まで象が暮らしていたのです。

浜北人と三ヶ日人
天竜区から浜名区にかけて連なる石灰岩地帯に沿って、現存するうちでは本州最古の人類化石となる浜北人やそれに続く三ヶ日人の化石人骨が見つかっています。

浜松市域を縦断する「中央構造線」
日本列島最大の断層帯、中央構造線が縦断する市内の数カ所で実際の断層を観察することができます。市内には化石の産地も各地にあります。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
 (別ウィンドウが開きます)
(別ウィンドウが開きます)