緊急情報
ここから本文です。
更新日:2014年1月14日
文化財情報vol.72
浜松市文化財情報/Vol.72
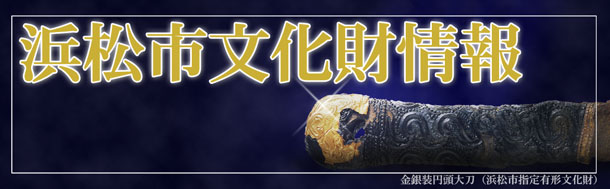
Vol.72平成26年1月15日
復元工事進む、浜松城天守門

浜松市公園課では、中区元城町にある浜松城跡(浜松市指定史跡)の歴史的な魅力を高めるため、積極的な整備工事を進めています。平成24年度から平成25年度にかけては、浜松城の中枢、天守曲輪の正門にあたる「天守門」の復元工事を実施しています。
いにしえの浜松城
浜松城の天守曲輪には、第二代城主である堀尾吉晴の在城期(1590~1600年)に壮大な天守が建築されたとみられますが、江戸時代の初期には喪失しています。一方、天守門は江戸時代を通じて維持され、明治6年(1873)に解体されるまで、浜松城を代表する象徴的な姿を保っていました。江戸時代に浜松城を描いた絵図には、櫓門(やぐらもん)とよばれる二階建ての立派な天守門が描かれています。
天守門を復元する
 軒瓦
軒瓦
かつて存在した天守門の詳細をさぐるため、浜松市文化財課では、平成21年度から24年度にわたり天守門跡の発掘調査を行い、建物の痕跡を確認いたしました。天守門の跡地からは、長軸1.0~1.4mほどの大型の礎石と、礎石の抜き取り穴が見つかり、門柱の配置や門扉の大きさが判明しました。また、建物の屋根に葺いた瓦や鯱瓦(しゃちがわら)の一部なども出土し、建物のおおよその年代が推定できました。天守門の二階にあたる土塁部分の調査では、壁からはがれた漆喰の痕跡や天守門の両側に延びていた土塀の瓦が出土し、櫓の大きさも想定できるようになりました。
発掘調査で得られた詳細なデータをもとに、天守門の寸法が精度高く求められました。また、遠州地方に残る江戸時代の城郭の門の事例をもとに、外観のデザインも検討され、厳密な時代考証を経た設計図が公園課によって作成されました。文化財課も時代考証などを中心に、公園課が推進する復元事業に協力しています。
復元天守門は、伝統的な木造構造によって建てられています。平成26年1月現在、二階の櫓部分がほぼ完成し、室内からは地元産の木材をふんだんに使った骨組みを見ることができます。櫓の屋根には、発掘調査による出土品を精巧に模した瓦が葺かれています。屋根瓦の端には巴文(ともえもん)や唐草文(からくさもん)といった模様がつけられた軒瓦が連なり、棟の両端には想像上の動物、鯱(しゃち)をかたどった瓦が乗せられています。鯱瓦も発掘調査による出土品をもとにした精緻な検討が加えられ、復元されました。

櫓内部の木組み
この春、公開!
復元天守門は平成26年4月に一般公開の予定です。こだわりの復元建築の完成をどうぞご期待下さい。

復元された鯱瓦
殿畑遺跡の発掘調査をしました!
 発掘調査区全景
発掘調査区全景
殿畑(とのはた)遺跡は、北区三ヶ日町三ヶ日の住宅街の中にある遺跡です。古くから石鏃(せきぞく)などの石器が拾える遺跡として地元の住民や研究者の間で知られていました。最初の発掘調査は、昭和35年(1960)に行われ、2日間の調査でリンゴ箱4箱分の土器と石器が出土しました。出土品の大半は縄文時代晩期から弥生時代前期の土器や石器で、その中に弥生時代前期の条痕文(じょうこんもん)土器と遠賀川(おんががわ)式土器の2種類の土器が混じって出土しました。遠賀川式土器とは、北部九州の遠賀川下流の遺跡で出土する土器様式で、稲作の伝播とともに各地へ拡散したと考えられており、この土器の出土から、殿畑遺跡は三ヶ日地区で最初に稲作を開始した集落の跡と推定されています。
今回の発掘調査は、住宅の建設に先立ち、7月に約105平方メートルを対象に実施しました。周辺は住宅地に囲まれていますが、地下の遺跡は良好に残っており、縄文時代から戦国時代までの幅広い時期の遺構と遺物を検出しました。竪穴住居は確認できませんでしたが、柱穴と思われる小穴が多数見つかり、周辺から条痕文土器や弥生土器のほか、石器が多く出土しました。特に石斧が30点近く出土し、その中には未完成品と思われるものがあることから、集落の中で石器作りをしていたと推定されます。また、鎌倉時代に掘られた長方形の穴の中から完全な形の山茶碗と小皿が出土しました。出土状況から鎌倉時代の墓の副葬品と考えられます。
殿畑遺跡でこれまでに発掘された面積は僅かですが、多数の土器や石器の出土から、縄文時代から弥生時代にかけて三ヶ日地区の中心的な集落であったと推定されます。

出土遺物
文化財日記抄
12月には、こんな調査活動などを行いました。
|
4日 |
(水曜日) |
南区高塚町 |
高塚町村西遺跡工事立会い |
|---|---|---|---|
| 北区引佐町 | 木造釈迦如来及両脇侍像現状調査 | ||
| 5日 | (木曜日) | 北区細江町 | 東林寺山門保存修理委員会 |
| 6日 | (金曜日) | 北区引佐町 | 実相寺庭園現状調査 |
| 8日 | (日曜日) | 西区雄踏町 | 農村歌舞伎活性化プラン映像作成立会い |
|
北区細江町 |
文化財防災フィールドワーク「引佐細江を襲った津波跡」 |
||
| 天竜区春野町 | 瑞雲院山門上棟式 | ||
| 10日 | (火曜日) | 天竜区二俣町 | 第2回文化財保護審議会 |
|
11日 |
(水曜日) |
浜北区染地台 |
絶滅危惧種調査 |
|
12日 |
(木曜日) |
中区田町 |
浜松宿工事立会い |
| 13日 | (金曜日) | 中区葵東~西区大山町 | 姫街道の松並木現状調査 |
| 14日 | (土曜日) | 西区雄踏町 | 農村歌舞伎活性化プラン映像作成立会い |
| 15日 | (日曜日) | 中区中央一丁目 | 浜松戦国塾(第2回)「浜松戦国の山城」受講者60人 |
| 16日 | (月曜日) | 西区大山町 | 姫街道の松並木保護作業 |
|
17日 |
(火曜日) |
西区篠原町 |
国方遺跡予備調査 |
| 18日 | (水曜日) | 中区肴町 | 出前講座「肴町の歴史」受講者22人 |
|
20日 |
(金曜日) |
天竜区佐久間町 |
準絶滅危惧種聞き取り調査 |
|
21日 |
(土曜日) |
北区引佐町 |
寺野のひよんどり後継者育成事業現地調査 |
|
24日 |
(火曜日) |
中区蜆塚二丁目 |
歌謡遺跡予備調査工事 |
| 南区堤町 | 堤町村東遺跡予備調査 | ||
| 北区都田町 | 都田山十六遺跡予備調査[~25日] | ||
|
25日 |
(水曜日) |
天竜区水窪町 |
冬休み子ども体験教室(カブト作り)講師 |
| 26日 | (木曜日) | 北区引佐町 | 寺野のひよんどり後継者育成事業現地調査 |
| 天竜区水窪町 | 宝篋印塔現地調査 |
文化財イベント
|
県指定無形民俗文化財「横尾歌舞伎」 |
平成26年2月2日(日曜日) 午後1時~午後5時頃/開明座(北区引佐町横尾) |
|---|---|
|
文化財講座 |
平成26年2月9日(日曜日) 申込:往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、「文化財防災講座申込」と書いて文化財課へ(〒430-8652中区元城町103-2) |
|
市指定有形文化財「東林寺山門」 |
平成26年2月23日(日曜日) |
浜松の自然災害史(10)湖辺に残る災害の記憶
~この記事は、浜松市メールマガジンとリンクしています~
浜名湖の北端、北区三ヶ日町と細江町一帯は奥浜名湖と呼ばれ、多くの景勝地があります。古来より浜名湖の自然は湖辺に住む人々にとって多くの恩恵をもたらすとともに、時として水にまつわる災害となって人々を苦しめてもきました。
三ヶ日地区には、地震による地殻変動で湖に沈んだ2つの場所の伝承が残されています。1つは津々崎集落南側の猪鼻湖中にある浅瀬で、「沖の瀬御殿」と呼ばれている地点です。ここは昔、病気の美しい娘の治療のため湖辺に造った御殿の跡と伝えられています。かつて陸地だった場所が地殻変動により水没し、伝説として語り継がれていると考えられます。もう1つは現在の東名高速道路浜名湖サービスエリアの西側の沖合にある「高屋の瀬」と呼ばれる浅瀬です。ここにはかつて数百戸からなる村がありましたが、明応7年(1498)に発生した明応地震による大津波で、一瞬にして村は壊滅し、湖底に沈んだと伝えられています。これらはいずれも伝承ではありますが、奥浜名湖における地震による地殻変動と津波災害を示すものと言えるでしょう。
嘉永7年(1854)に発生した安政東海地震では、東海地方に甚大な被害をもたらしたことが、様々な記録に残っています。姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館に展示されている『安政地震津波災害絵図』には、引佐細江を津波が遡上し、気賀の街まで押し寄せたこと、津波が引いた後は水田が泥田化したことが描かれています。三ヶ日の水没した村の伝承などとともに、浜名湖を遡上した奥浜名湖地域を襲った大津波の生々しい記憶と言えます。
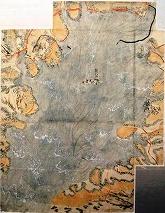
『安政地震津波災害絵図』押し寄せる津波が描かれている
編集後記
新しい1年が始まりました。今年は午年、かつて馬は「神の乗り物」と考えられていました。古くから現代に至るまで、人と深く関わりを持ってきた馬…昨年発掘した郷ヶ平6号墳からは、鹿の他に、馬の埴輪も出土しました。現在、整理作業が進められています。さて、今年はどんな発見があるのでしょうか。皆様にとって、万事ウマくいく年となりますように。
→「文化財情報」バックナンバーに戻る
→文化財トップに戻る
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください