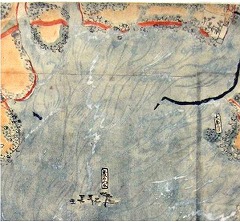緊急情報
ここから本文です。
更新日:2013年12月15日
文化財情報vol.71
浜松市文化財情報/Vol.71
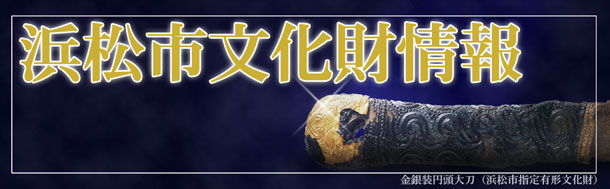
Vol.71平成25年12月15日
関西で市内の民俗芸能が披露されました!

去る11月9日(土曜日)、市内の民俗芸能が関西地方で披露されました。大阪市内では横尾歌舞伎、京都市内では西浦の田楽が上演され、多くの方が浜松の文化を鑑賞されました。
横尾歌舞伎(北区引佐町/県指定無形民俗文化財)
大阪市内で行われた「大阪静岡県人会創立100周年記念行事」に、静岡県内の民俗芸能を代表して、横尾歌舞伎保存会が参加しました。10月の定期公演を終えてから一月も経たない時期の外部公演ということで、保存会の皆さまは定期公演の熱気そのままに稽古を重ねました。また、1年以上前から主催者(静岡県・大阪静岡県人会)との打ち合わせや会場下見などの準備を進め、万全の体制で当日を迎えました。
当日は、まだ夜も明けきらない早朝4時30分から衣裳や舞台用具を詰め込み、引佐を出発しました。会場到着後、休む間もなく関係者全員が花道の組立や背景幕の設置を行いました。役者と下座音楽は位置合わせ、マイクチェック、照明チェックほか、演出面を含めて入念にリハーサルを行いました。一方、楽屋では、床山衣裳部が出演者全員分のかつらと衣裳を揃え、化粧を終えた役者に対して手際良く着付けを行っていきました。

花道設営中

化粧中

着付け
そしていよいよ本番、森山誠二副知事、石川嘉延前知事などのあいさつの後、横尾歌舞伎「白浪五人男 稲瀬川勢揃の場」が披露されました。今回は、あえて直前の定期公演で上演したものでなく、静岡県ゆかりのセリフが随所にでてくる演目を上演しました。会場全体に響き渡る柝の音で幕が開き、特別に設けられた花道から役者が登場すると、会場からは感嘆の声と盛大な拍手が湧き起こりました。『問われて名乗るもおこがましいが 生まれは遠州浜松在・・・』『・・・盗みはすれど非道はせず 人に情けを掛川から 金谷をかけて宿々で・・・』など、登場人物の一人、日本駄右衛門の口から静岡県ゆかりのセリフが発せられ、見えが切られると、観客の視線は舞台に釘付けとなりました。五人男と捕り手の立ち廻りが演じられる最後の場面では、客席からたくさんの“おひねり”が投げ込まれ盛況のうちに幕を閉じました。
遠く故郷を離れて関西地方で暮らす静岡県出身の皆さまに、郷土の文化を感じていただくことができました。

会場からたくさんのおひねりが!
西浦の田楽(天竜区水窪町/国指定重要無形民俗文化財)
京都市内で行われた「京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター公開講座」に、西浦田楽保存会の能衆19人が出演しました。西浦の田楽は、本来、精進潔斎した能衆が観音様の祭りとして行うものであり、見せるための芸能ではありませんが、今回は主催者との協議を重ね特別に上演することとなりました。
当日は、地能・はね能あわせて多彩な15番の舞が演じられ、解説・休憩を含め4時間にわたり上演されました。大勢の観客は最後まで熱心に鑑賞し、西浦の田楽が醸し出す荘厳で神秘的な世界観と能衆の情熱を体感していただくことができました。
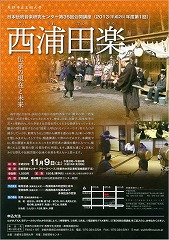
《募集》文化財防災ボランティア養成講座を開催いたします
大規模な災害が発生した場合、広範に被災した文化財の保全、迅速な仮復旧は緊急の課題となります。また地震や津波の発生が予想される地域では、防災・減災が喫緊の課題です。当課では、静岡県文化財保護課とも協力して、平成23年度から文化財防災ボランティア養成講座を開催してまいりました。今年度も、新たなボランティアの参加を期待します。
また、12月8日には、昨年度までの養成講座参加者を中心に、度重なる災害古記録が残る浜名湖畔の気賀で、フィールドワークを実施いたしました。旧姫街道を歩きながら、安政東海地震の津波が及んだ範囲を想像しました。今後も養成講座修了生を中心に現地調査も計画してまいります。

フィールドワークの様子(国登録文化財・天浜線駅舎)
<講座のご案内>
| 期日 | テーマ | 講師 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 3月2日(日曜日) | 開会あいさつ 1.文化財修復の実技 |
文化財課 NPO文化財を守る会 |
博物館講座室 |
| 3月9日(日曜日) | 2.県文化財等支援員の内容 3.大船渡派遣報告 |
県文化財保護課 文化財課 |
博物館講座室 |
| 3月16日(日曜日) | 4.市内の文化財保護の課題 まとめ、修了式 |
文化財課 | 博物館講座室 |
費用:受講料無料。ただし「1.文化財修復の実技」は実費(材料費1,000円程度)必要。
定員:50名(申込多数の場合は抽選)※全3回受講可能な方対象
応募方法:往復はがきに住所・氏名を書いて、浜松市文化財課「文化財ボランティア講座」係(〒430-8652浜松市中区元城町103-2)まで郵送。2月21日消印有効。
備考:広報はままつ2月5日号に掲載予定。
引佐細江を襲った津波の絵図(姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館にて展示中)
文化財日記抄
11月には、こんな調査活動などを行いました。
|
2日 |
(土曜日) |
天竜区佐久間町 |
川合花の舞伝承状況現地調査 |
|---|---|---|---|
| 3日 | (日曜日) | 西区雄踏町 | 農村歌舞伎活性化プラン映像作成立会い |
| 7日 | (木曜日) | 北区引佐町・細江町 | 出前講座 |
|
北区神宮寺町 |
北神宮寺遺跡工事立会い |
||
| 8日 | (金曜日) | 中区田町 | 歴史的建造物防災図上訓練 |
|
9日 |
(土曜日) |
天竜区水窪町 |
浜松戦国山城まつり来場者600人 |
| 大阪市天王寺区 | 横尾歌舞伎外部公演随行 | ||
|
11日 |
(月曜日) |
天竜区春野町 |
瑞雲院山門保存修理現場見学会(犬居小1~3年生) |
| 13日 | (水曜日) | 南区新橋町 | 新橋町村東遺跡工事立会い |
|
天竜区春野町 |
瑞雲院山門保存修理現場見学会(犬居小4~6年生) |
||
| 15日 | (金曜日) | 東京都千代田区 | 第9回はままつ「やらまいか」交流会PRブース出展(無形民俗文化財) |
|
17日 |
(日曜日) |
豊橋市 |
三遠南信ふるさと歌舞伎交流豊橋大会運営状況確認 |
| 19日 | (火曜日) | 天竜区二俣町 | 清竜中学校伝統芸能伝承活動現地確認 |
|
20日 |
(水曜日) |
中区池町 |
浜松宿工事立会い |
|
21日 |
(木曜日) |
中央図書館 |
近現代建築資料所在確認調査 |
| 東区笠井町 | 笠井上組遺跡工事立会い | ||
|
24日 |
(日曜日) |
中区・市民協働センター |
浜松戦国塾(第1回)受講者45人 |
| 西区雄踏町 | 農村歌舞伎活性化プラン映像作成立会い | ||
|
25日 |
(月曜日) |
天竜区春野町 |
瑞雲院山門保存修理委員会 |
| 26日 | (火曜日) | 本庁 | 姫街道の松並木保存管理庁内連絡会議(第2回) |
| 中区・県居協働センター | 梶子遺跡講座受講者11人 | ||
| 天竜区二俣町 | 清竜中学校伝統芸能伝承活動現地確認 | ||
|
29日 |
(金曜日) |
中区・浜松城天守閣 |
浜松城跡出土鯱瓦展示[~12月8日] |
埋蔵文化財予備調査
| 11日 | (月曜日) | 東区有玉西町 | 千人塚古墳群[~18日(月曜日)] |
|---|---|---|---|
| 19日 | (火曜日) | 東区笠井町 | 笠井若林遺跡 |
| 21日 | (木曜日) | 南区高塚町 | 高塚遺跡 |
| 26日 | (火曜日) | 北区細江町 | 石岡遺跡 |
| 27日 | (水曜日) | 西区篠原町 | 国方遺跡 |
文化財イベント
|
国選択無形民俗文化財「滝沢のシシウチ行事」 |
平成26年1月1日(水曜日・祝日) |
|---|---|
|
重要無形民俗文化財「遠江のひよんどりとおくない」 |
平成26年1月3日(金曜日) 午後1時頃~午後7時頃/泰蔵院(天竜区懐山) |
|
重要無形民俗文化財「遠江のひよんどりとおくない」 |
平成26年1月3日(金曜日) |
|
国選択無形民俗文化財「滝沢のシシウチ行事」 |
平成26年1月4日(土曜日) |
|
重要無形民俗文化財「遠江のひよんどりとおくない」 |
平成26年1月4日(土曜日) |
浜松の自然災害史(9)掘り出された災害の痕跡
~この記事は、浜松市メールマガジンとリンクしています~
文化財課では、土中に埋もれた遺跡の有無を確認するため、日々、発掘調査を実施しています。地面の下には、人びとの生活の痕跡とともに、過去におこった災害の跡も埋もれています。平成25年9月、東区で実施した発掘調査で、見慣れない奇妙な地層を確認いたしました。通常、地層は水平に重なっているだけなのですが、この遺跡では、地面が裂けたような跡があり、その隙間には砂が入り込んでいたのです。
この奇妙な地層の様子は、「噴砂(ふんさ)」とよばれる液状化現象の痕跡です。当地に起こった地震により、地面が揺さぶられ、下層にあった砂が地表に噴き出したものと考えられます。最初の観察で、「地面が裂けた」と見立てたのは誤りで、正しくは、砂が地面を裂いて地表に噴きあがった跡だったのです。噴きあがった砂は、弥生時代(約2000年前)の黒色の地層を突き破り、奈良時代以降(8世紀頃)の褐色の地層によって覆われていました。つまり、今回の発掘調査で確認した噴砂は、この間に地震があったことを示していると解釈できます。
飛鳥時代(7世紀)以前の出来事を記した『日本書紀』には地震の記録もみられます。中でも、684年に起こった地震は、「白鳳の南海・東海地震」と呼ばれ、当地域にも大きな被害をもたらしたと考えられます。地震の規模をあらわすマグニチュードの試算値は8.0。当時の民衆が住まいとしていた竪穴住居などは倒壊するものが多かったとみられます。今回の発掘調査で確認した噴砂は、どの時代の地震によるものか確定できませんでしたが、記録にある白鳳地震によって引き起こされたものである可能性は十分に考えられるでしょう。

噴砂の跡
編集後記
平成25年もあとわずかとなりました。来年は午年です。ウマの化石では、約6,000万年の間に、肢(あし)の指の数が減少し第3指一本となり、体高は約30cmから大型化して現在の大きさへと、草原での高速走行や食物に適応した形態へ進化してきたことがみられます。草原を駆け回る駿馬のように、元気あふれる良い年となりますよう、お祈り申し上げます。
→「文化財情報」バックナンバーに戻る
→文化財トップに戻る
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください